セブン-イレブン、茨城県城里町で買い物弱者対策として移動販売「セブンあんしんお届け便」の運用開始
2011/05/13 06:43
 【セブン&アイホールディングス(3382)】の子会社でコンビニエンスストアのセブン-イレブンを運営するセブン-イレブン・ジャパンは2011年5月12日、同年5月18日から「買物支援」として同社では初の取り組みとなる移動販売『セブン安心お届け便』の運用を開始すると発表した。茨城県城里町での運用となる(【発表リリース】)。
【セブン&アイホールディングス(3382)】の子会社でコンビニエンスストアのセブン-イレブンを運営するセブン-イレブン・ジャパンは2011年5月12日、同年5月18日から「買物支援」として同社では初の取り組みとなる移動販売『セブン安心お届け便』の運用を開始すると発表した。茨城県城里町での運用となる(【発表リリース】)。
↑ 「セブン安心お届け便」(車両本体)
少子高齢化や人口減少の進展、ならびに生鮮食料品販売店などの小売店舗をはじめさまざまな拠点数の減少といった社会環境の変化を背景に、住んでいる地域で日常の買物をする上で、不便・困難を感じる人、いわゆる「買い物弱者」が増加している。このような日々の買物に難儀している人への支援は高齢化社会において、重要かつ解決優先順位の高い課題。
セブン-イレブン側ではこの「買い物弱者」問題を、地域における小売事業者の立場から重要視。買物や食生活をサポートするという点で、同社が果たすべき役割は大きいと認識し、今回の「移動販売専用の車両」の新規開発に至った。
今後は行政と連携するとともに、フードデザート(食品・菓子果物、ではなく、食品・砂漠。生鮮食料品の供給システムが立ちゆかなくなり、社会的な弱者に様々な悪影響が及ぶ問題。「買い物弱者」問題と同義)問題に詳しい専門家からもアドバイスを受けながら、茨城県城里町(セブン-イレブン常北下古内店)にて、本格的な移動販売の運用を開始する。
同店舗では即食性の高いおにぎりやお弁当、パンや飲料などを中心に、日常生活において使用頻度の高い生活必需品に絞り込んだ商品約150アイテムを移動販売車へ搭載。城里町周辺の集落センターなどへの巡回販売を展開していく。また、茨城県内においては、既に一部店舗で実施中の御用聞き(配達)サービスも、順次拡大していくとのこと。

↑ 日よけ・雨の日対策用に、フードの取り付けが可能
要は、これまでコンビニエンスストアの店舗がその周囲の商域に住まう人たちに来店してもらうことのみを前提としていたのに対し、今回の「セブンあんしんお届け便」は店舗自身の運営を続けつつ、移動販売車両の拠点としても店舗を活用。コンビニの商域内に居住していながら店舗までの来店が難しい人や、その商域の周辺外域かつ移動販売車両の行動範囲内にある地域の人に、コミュニティの集会場(今件なら集落センターや福祉センター、事業所など)を介して販売などのサービスを「お届け」していくことになる。予定では1日4-5か所を巡回して販売する。営業時間は(目安として)月曜-金曜、10時-15時。
この仕組みなら既存のインフラを最大限に活用できるだけでなく、商域のさらなる拡大、そして何より地域への浸透と貢献をより一層推し量れる点など、メリットは多い(リリースでも言及されているように、運用上でのノウハウの蓄積やコスト問題など、しなければならないことは多いが)。
そして今件の「セブン安心お届け便」の車両スタイルを見て気がついた人もいるだろうが、今回の仕組みは【ローソン、移動販売車で岩手県へ・移動販売開始】でも紹介した、コンビニの移動型簡易店舗の形状・システムとほぼ一致する。つまり今後「買い物弱者」対策として「セブン安心お届け便」のシステムを普及させ、車両の配備を(予備も含めて余裕を持って)推し進めることで、何か不測の事態が発生した場合でも可及的速やかに現地(災害被災地など)に臨時店舗を展開し、生活必需品などを提供できる支援体制を「備え」として保有できることになる。つまり平時は「買い物弱者対策」、有事は(運用を工夫し予備も投入することで)「災害支援」に用いることができる、極めて有益な「機動予備軍」を有することになる。
通常使用時の運用コストは一般の店舗よりもかさむことが予想されるが、社会貢献の度合いや「保険」としての考え方など、益となる部分も多い。今後の展開には大いに期待したいところだ。
■関連記事:
【「買い物弱者」を支える事業に2/3・上限1億円まで補助金】
スポンサードリンク
関連記事
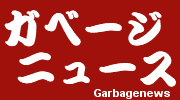
 最新情報をRSSで購読
最新情報をRSSで購読